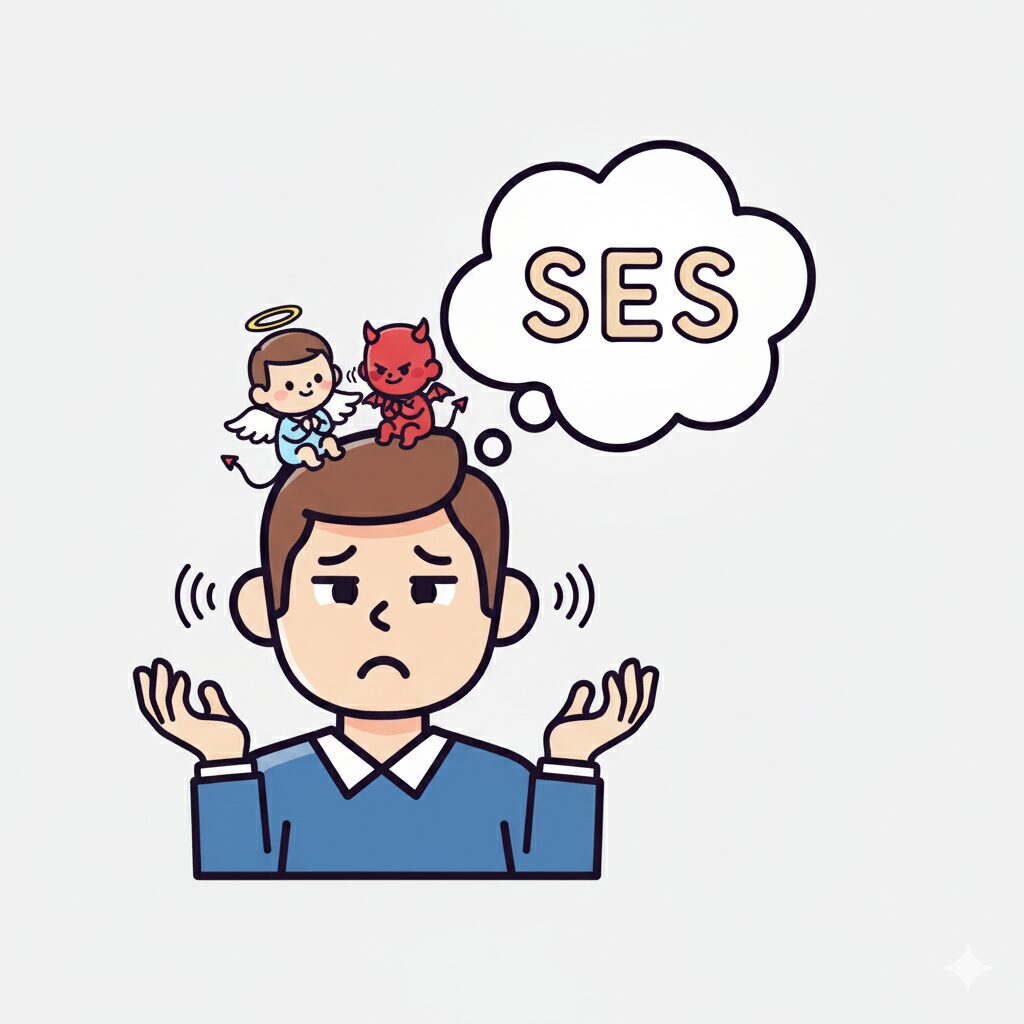「SESだけはやめとけ」
ネット上には、まるでそれが絶対の真理であるかのように語られていますよね。
僕は新卒未経験でよく分からずに飛び込んでしまった業界がSESでしたが、後にその言葉を知って愕然としたことをよく覚えています。
そのまま15年間SES業界に身を置き、今は訳あってSES業界を離れていますが、SESエンジニアとしてリアルな経験をしてきた僕だからこそ断言できることがあります。
結論:「SESはやめとけ」はかなり本当で、ちょっとだけ嘘
いきなり曖昧な答えですみません、、でも、これが一番正直な答えになります。
ネットで語られる「SESの闇」は、確かに存在します。僕も実際に地獄のような現場を経験しました。でも、SESだからこそ得られた経験やスキルがあるのも事実です。
大事なのは、「やめとけ」という言葉を鵜呑みにするのではなく、SESという働き方のメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合っているかどうかを判断することだと思います。
この記事では、僕が15年間で実際に体験した「リアルなSES」について、良いも悪いも包み隠さずご紹介します。
この記事を読み終える頃に、あなたがSESという働き方を選ぶべきかどうか、少しでも助けになっていれば嬉しいです。
「SESはやめとけ」と言われる7つのデメリット
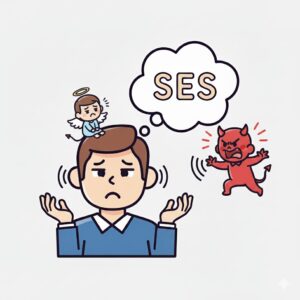
まずは、皆さんが一番気になっているであろう「闇」の部分から。なぜSESは「やめとけ」と言われてしまうのか。僕のリアルな体験談と合わせて、7つのデメリットをご紹介します。
デメリット1:給料が上がりにくい(会社の取り分が大きい)
SESは、客先から支払われる「単価」の中から、会社の利益(マージン)を差し引いた額が給料になります。
例えば、あなたの単価が月100万円だったとしても、会社が60%のマージンを取っていれば、あなたの給料の原資は40万円。そこから社会保険料などが引かれます。
つまり、どれだけ現場で頑張って評価されても、自社の給与テーブルやマージン率が変わらない限り、給料が劇的に上がることは少ないんです。
【僕が感じたリアルな話】
同じ現場に3年も4年もいると、そのプロジェクトのいろはをかなり理解している立場になっています。客先のリーダーさんからも高評価をいただき、何気ない日頃の会話の中で「○○さんの単価アップしましたもんね」みたいな話を初めて聞いたのですが、僕の給料には全く反映されていませんでした。会社だけが潤っていたんだろうなと思います。どれだけ頑張っても給料に反映されないのか…と、モチベーションダウンしまくりでした。
デメリット2:客先ガチャでキャリアが左右される
これはSESの宿命とも言える問題です。
どんな現場(客先)に配属されるかによって、経験できる業務内容、使用する技術、人間関係が全く変わってきます。
- 最新技術に触れられる「アタリ」現場
- 誰でもできる単純作業ばかりの「ハズレ」現場
この「客先ガチャ」に外れると、望んでいたスキルが全く身につかず、時間だけが過ぎていく…なんてことになりかねません。また、全くスキルが身についていないまま経験年数だけは積み重なっていくので、「○○年目のエンジニアなのにこんなこともできないの?」という状況になってしまい、新しい客先に配属されづらくなる悪循環に陥ります。
【僕が感じたリアルな話】
いくつ目の現場だったかは覚えていませんが、まだ入社5年目以内の話です。たしかそこは詳細設計フェーズから参画した現場でしたが、プロジェクトのメンバみんな誰も何も会話せず、ただひたすらキーボードをたたきまくっている異様な雰囲気の現場に配属されました。質問しようにも絶望的に質問しづらい空気で、季節は夏でプロジェクトルームは地下だったというのも重なり、暑く重苦しい空気だった現場ということだけが強く印象に残っています。(監獄と呼んでいました)
デメリット3:会社の先輩や同僚との繋がりが薄い
基本的に少人数、場合によっては一人で客先に常駐することになるため、自社の社員と顔を合わせるのは月に一度の帰社日くらい、という会社も珍しくありません。
そうなると、
- 仕事の悩みを気軽に相談できる先輩がいない
- 同期と切磋琢磨する機会がない
- 会社のイベントに参加しても、知らない人ばかりで気まずい
といった孤独を感じやすくなります。特に未経験から入ったばかりの頃は、精神的にキツいと感じるかもしれません。
【僕が感じたリアルな話】
自社の社員とは本当に月に一度の帰社日だけしか顔を合わす機会がありません。と言うか、その帰社日すら帰社できない(帰社する気が無い)社員も少なくないので、本当に自社の社員との関わりは薄いです。先輩に飲みに連れて行ってもらうとか、可愛い後輩が入ってきたとか、そういう世界とは無縁だったと思います。
デメリット4:評価制度が不透明になりがち
あなたの働きぶりを直接見ているのは自社の上司ではなく客先の社員です。
自社の上司は、あなたと月に1回面談するか、営業担当から伝え聞く客先の評判でしか、あなたを評価できません。
デメリット1と近い内容になりますが、現場での頑張りが正当に評価されず、給与や昇進に反映されにくいという問題が起こりがちです。
【僕が感じたリアルな話】
年に一度、人事考課の場で上長から評価されるシーンがありましたが、正直「普段の自分を全然見てないあなたに何が分かるんですか?」という気持ちが強かったです。どれだけ頑張ってもそれが直接評価に反映されず(反映されても給料にまで反映されるかどうか怪しいですが…)、でも逆に何かをやらかした場合は客先からのクレームと言う形でしっかり評価ダウンには繋がる、何かフェアじゃないなと言う気はしました。
デメリット5:帰属意識が持ちにくい(まるで個人事業主)
毎日通うのは客先のオフィス。話す相手も客先の社員。自社のオフィスにはほとんど行かない…。
そんな生活が続くと、「自分は一体どこの会社の人間なんだろう?」という気持ちになってきます。
良く言えば自由ですが、悪く言えば「会社に守られている」という感覚が薄く、強い帰属意識は持ちにくいかもしれません。
【僕が感じたリアルな話】
普段は常駐している客先の社員として振る舞い、そこからさらに別の客先に常駐させられるようなケースもありました。自社のものではない名詞もいくつも持たされました。普段の仕事においては自社が一番関わらず、いいように使われている感がありましたので、本当にいったい自分はどこに所属している何者なんだと感じることは少なからずありました。
デメリット6:会社の福利厚生を使えないことがある
例えば「自社オフィスのおしゃれなカフェが使える」「フリードリンクがある」といった福利厚生があっても、客先常駐のエンジニアには全く関係ありません。
また、住宅手当なども「常駐先の場所によって不公平が出るから」という理由で、一律で支給されない会社もあります。
【僕が感じたリアルな話】
社員はみんなどこかの現場に売り飛ばされて行きますからね、自社オフィスには社員はほとんど残りませんでした。おしゃれなカフェ、フリードリンクなんてものはそもそも無塩でした。とりあえず住宅手当なんてものはありませんでした。
デメリット7:多重下請けの末端だとスキルアップが難しい
いわゆる「SESの闇」の象徴が、この多重下請け構造です。
元請け(クライアント)から二次請け、三次請け…と仕事が流れていく中で、末端のエンジニアに回ってくるのは、システムの根幹に関われないテスト業務や運用保守だけ、というケースがあります。
このような現場に長期間いると、スキルが全く伸びず、キャリアが停滞してしまうリスクがあります。
【僕が感じたリアルな話】
自信を持って言えますが、多重下請けは普通に蔓延っています。僕も常駐先からさらに別の会社に常駐させられる多重下請けの被害?を受けていて、そのときは得に何か被害を受けている感覚は無いのですが、今考えると、そんな自社の社員でもないただの労働力要員に親切丁寧にものを教えてくれる人はあまり居ないので、用が済んだらパパっと切られるだけの使い捨て要員でした。スキルの伸びと言う意味で期待できる環境ではないですね。
僕がSESを15年続けた9つのメリット

…と、ここまでデメリットばかりを並べて「やっぱりSESはヤバいじゃないか!」と思われたかもしれません。
でも、待ってください。SESにはSESのメリットも確かにありますので、それをご紹介していきます。
メリット1:短期間で多様な技術・業界の経験が積める
自社開発企業だと、基本的に自社のサービスやプロダクトにしか関われません。
しかしSESなら、常駐する客先や関わるプロジェクトによって、短い期間の中でさまざまな技術に触れることができます。
- 1年目:金融系のシステム開発(Java)
- 2年目:Webサービス系のインフラ構築(AWS)
- 3年目:スマホアプリ開発(Swift/Kotlin)
…といったように、短期間で幅広い経験を積むことができます。これは、自分の適性を見極めたい若手エンジニアにとって、大きなアドバンテージになります。
【僕が感じたリアルな話】
大変と言えば大変なんですけど、良い感じの期間で色々なPJに関わることができれば、広く色々な知識を身に着けることができるのは間違いありません。ただこれも客先ガチャによる部分が大きかったりするので、僕は運が良かったのかな…とも思います。
メリット2:大手企業のプロジェクトに参加できるチャンスがある
誰もが知っているような大手通信会社、銀行、メーカーなどのプロジェクトに、メンバーとして参加できるチャンスがたくさんあります。
新卒で入社するのは難しいような有名企業で、最先端のシステム開発の現場を肌で感じられるのは、SESならではの魅力です。
【僕が感じたリアルな話】
僕はそういうプロジェクトにがっつり参加した経験はありませんでしたが、それでもちょこちょこと関わったことは確かにあります。特に印象に残っているもので言うと、品川にある某巨大企業と関わったり、あの有名な冷凍食品の会社さんのプロジェクトに関わってみたり、いろいろな業種のお仕事に関われました。
メリット3:人間関係をリセットしやすい
会社員にとっての一番の悩みは「人間関係」っていう人は少なくないですよね。
もし、会社の上司や先輩、客先に苦手な人が居たとしても、SESならその負担が最小限に抑えられます。相手が自社の人間であればそもそも顔を合わす機会がめちゃくちゃ少ないですし、相手が客先の人間だった場合は、契約期間が終わればその人たちとはもう会うことはありません。
苦手な人との関係に悩み続ける必要がなく、定期的にリセットできるのは、精神衛生上、非常に大きなメリットです。
【僕が感じたリアルな話】
人間関係の悩みっていうのは大多数の人が抱えがちだと思います。あの人イヤなんだよなー…とか、そういうのが原因で転職にまで発展するケースも珍しくない中、SESの場合はその関係性が限定的なものであることがほとんどなので、あとちょっと我慢すれば…!というメンタルで乗り切りやすいと思います。
メリット4:待機期間をスキルアップに使える
一つの現場が終わり、次の現場が決まるまでの期間を「待機期間」と呼びます。
この期間は、会社としては発生してほしくない期間であることは間違いありませんが、客先の事情等でタイミングが合わず1ヶ月間待機しなくてはならない~とかも起こり得ます。
この期間は、給料をもらいながら資格取得の勉強や自己のスキルアップに時間を費やすことができますので、かなり嬉しい時間になります。
【僕が感じたリアルな話】
正直、15年間のSESの中でほとんど待機期間はありませんでした(営業が無駄に優秀だったのかもしれません)が、あのときは時間の流れが穏やかだったな…と、ちょっとした良い思い出のような期間として印象に残っています。
メリット5:基本的には指示された作業をこなすだけで良い
メリットと呼んで良いのか微妙なラインですが、SESは何か頼まれごとがある場合に赴く形式ですので、その頼まれごと消化するだけ(お願いされたことを対応するだけ)で良い、責任の軽さがあります。
自社のプロダクトに関わった場合は、企画や提案等、ちょっと面倒そうな業務に頭を悩ます必要がありますが、SESの場合はそういった重い責任がのしかかるようなシーンはほとんどないと思います。
【僕が感じたリアルな話】
SESは詳細設計以降のフェーズの作業が回ってくることが非常に多く、その頃はやるべき内容が大体固まっています。言われたことをやるだけというのはある意味一番ラクなので、やりがいを感じられるかどうかは難しいところですが、仕事をただただお金を稼ぐための手段と割り切っている人からすればアリな気はします。
【自己診断】メリット・デメリットから分かるSESが向いている人・いない人
ここまで紹介したメリット・デメリットを踏まえて、どんな人がSESに向いているのか、僕なりにまとめてみました。
SESが向いている人の特徴
- 特定のやりたいことが決まっておらず、色々な経験を積みたい人
- ドライな人間関係を好む人
- 言われたことだけやってお金をもらえれば良いやという考えの人
SESが向いていない人の特徴
- 特定のプロダクトやサービスをじっくり育てていきたい人
- 給与や待遇で正当な評価をすぐに得たい人
- 会社への帰属意識や、同僚との一体感を強く求める人
- 指示待ちではなく、自ら企画や提案をしたい人
まとめ:SESは「働き方」の一つ。偏り過ぎな意見に惑わされずに正しく理解して判断することが大事!
「SESはやめとけ」
どちらかと言えば正直僕もそっち寄りではあるんですけど、この言葉だけを鵜呑みにして「SESは百害あって一利なし!」と考えてしまうのはちょっとどうかなと思います。
確かに、給料が上がりにくかったり客先ガチャがあったりといったデメリットは存在しますが、SESという働き方でしか得られない魅力があることも事実です。
大切なのは、ネットの噂に惑わされず、SESという働き方を正しく理解することですね。SESはエンジニアとして広く(浅く)いろいろな経験を積みやすい働き方だと思います。
例えば、最初はSESから始めて、ある程度経験を積んでから自社プロダクトを持つ会社に転職するというプランも全然アリだと思いますので、あなた自身のキャリアプランを考えたときに、SESが利用できそうであれば利用してしまうというのも全然アリではないでしょうか。